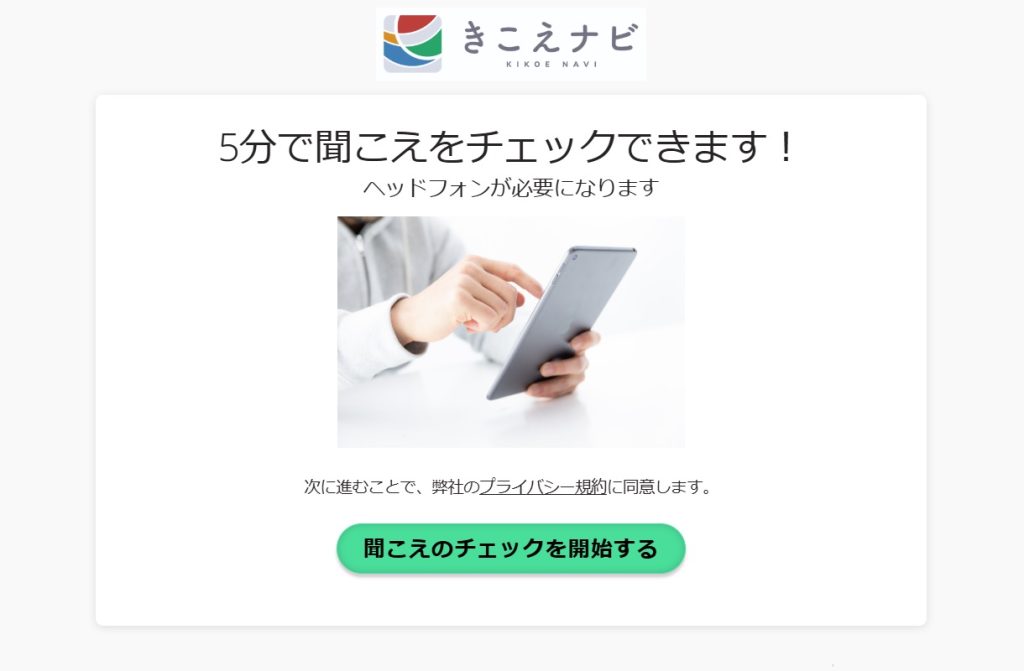3月3日は「耳の日」。日本では昭和31年に日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会が制定しました。
実はこの日は日本だけでなく、世界でも耳の健康を考える日として認識されています。
耳はただ音を聴くための器官ではなく、私たちの生活に欠かせない役割を果たしています。
今回は「耳の日」にちなみ、耳にまつわる驚きの事実や、日常生活で簡単にできるケア方法、耳の日のイベントなど盛りだくさんの情報をお届けします。
関連ページ:
目次
1 こんなに進化している?!補聴器の最新テクノロジーや、未来の耳の技術
近年、耳や聴覚に関するテクノロジーは飛躍的に進化しています。
補聴器もその一例で、かつては単純に音を増幅していましたが、最新の補聴器は驚くべき機能を搭載しています。
さらに、聴覚を補助するだけでなく、生活全般をサポートする新しい技術が続々と登場しています。
1-1 こんなことまでできる!最新補聴器の進化
補聴器は今や、ただ音を増幅するデバイスにとどまりません。最新の補聴器は、ユーザーの生活の質を向上させるために、驚くべき進化を遂げています。
ノイズキャンセリング機能
各補聴器メーカーから発売されている補聴器に、ほぼ標準搭載されているのが、騒音を抑える機能です。
日常にあふれるさまざまな音から、パソコンやエアコンのファンの音、交通騒音など、雑音を識別して抑え、人の声だけを聴き取りやすくしてくれます。
AI搭載
最新の補聴器にはAI機能が搭載されているものも。
ユーザーが今どんな環境にいるのか、補聴器が瞬時に判別して最適な音に自動調整したり、同じ環境にいても一人ひとり異なる音の好みに合わせて学習する補聴器など、さまざまな製品が登場しています。
スマホとつながる補聴器
補聴器がBluetoothでスマートフォンやテレビ、パソコンと簡単に接続でき、通話の音や音楽を直接耳に届けてくれます。
これにより、音楽や映画を楽しむ際も、快適に音を楽しむことができます。
また、専用アプリを使って音量調節や音質の調整、聞きたい方向のコントロールをしたり、万が一補聴器を紛失した場合でもGPSで探す機能なども登場しています。

関連ページ:2026年版:最新技術が搭載された補聴器のデザイン・機能・選び方
1-2 耳を使った新しい生体認証方法「耳介認証」と「耳音響認証」
耳の構造や音の伝わり方を利用した新しい生体認証技術も注目されています。
最近、耳を使った新しい認証方法が登場し、セキュリティや個人認証の分野での応用が進んでいます。
耳介認証
耳介(じかい)は、耳の外側に見える部分のことで、この部分の特徴をもとに個人を識別する技術です。耳の形状は一人ひとり異なるため、非常に高い精度で本人確認を行うことができます。この技術は、指紋認証や顔認証に代わる新たな選択肢として注目されています。
参考:耳介認証 – 入退室管理などセキュリティ情報メディア|SECURITY MEDIA
耳音響認証
耳の中の形状も一人ひとり異なるため、その違いを利用した生体認証です。イヤホン型のデバイスを使って音波を送り、その反響を利用して個人を識別します。
耳音響認証は、手を使わずに簡単に認証を行えるため、スマートフォンやデジタルデバイスでの利用が期待されています。
参考:人によって異なる耳穴の形状を音で識別する耳音響認証技術 | NEC
1-3 聴力が復活する?iPS細胞技術の活用
補聴器で失われた聴力を補うのではなく、聴力そのものを回復させる技術も研究が進んでいます。
特に注目されているのが、iPS細胞(人工多能性幹細胞)を用いて内耳の損傷を修復し、聴力を回復させる再生医療の研究です。
iPS細胞は、体のあらゆる種類の細胞に変化できる能力を持っており、聴覚に関わる細胞や組織の再生に応用することが期待されています。
聴覚に関しては、内耳の毛細胞の再生に関する研究が進んでおり、将来この技術が実用化されれば聴力を取り戻すことができるかもしれません。
参考:難聴をiPS細胞技術で治す時代がやってくる!? | 日本耳鼻咽頭科学会
2 耳を大切にするための簡単セルフケア
耳は体の中でも意外に繊細な部分ですが、私たちの日常生活ではそのケアが不足しがちになってしまうことも。
ここでは、耳の健康を長く保って聴力の低下を防ぐために簡単にできる耳のセルフケア方法をご紹介します。
2-1 正しい耳掃除の方法
みなさんが日常的に行っている耳掃除。実は間違った方法で耳掃除をすると、耳にトラブルを引き起こす原因になります。ポイントをふまえて正しい耳掃除を実践しましょう。

ポイント① 耳掃除をやりすぎない
耳垢は本来、自然に外に排出されるものと言われています。過剰な耳掃除は外耳道の炎症や感染の原因にもなりますので、耳掃除は月に1~2回程度に留めましょう。
もし耳垢が気になる場合は、ぬるま湯で耳を軽く洗うか、耳掃除専用のクリーナーを使うのが安心です。
ポイント② 耳かきより綿棒を使う
硬い耳かきを使うと外耳道を傷つける恐れがありますので、綿棒を使って耳穴の入り口周辺を拭うようにしましょう。
ただし、綿棒を使って耳の奥まで掃除すると、耳垢が押し込まれてしまい、耳の奥で詰まってしまうことがあるため注意してください。
ポイント③ 耳鼻科医で耳垢を除去してもらう
自分でうまく耳掃除ができなかったり、耳に痛みやかゆみを感じる場合は、無理に自分で耳掃除をせず、耳鼻科医に相談しましょう。
「耳掃除くらいで病院なんて大げさ」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、専門医に相談して耳垢を除去してもらうのが安心です。
2-2 耳のマッサージ方法
耳のマッサージで耳の周りの筋肉をほぐし、耳の中の血流を改善することで、耳の健康を保つことができます。特に、ストレスや疲れを感じると、耳の筋肉も緊張してしまうので、リラックスするためにぜひ取り入れてみましょう。
耳のマッサージ方法
-
耳全体を手でくるみ、くるくると動かす
-
耳を親指と人差し指でつまみながら、上、下、斜め上、斜め下、横に軽く引っ張る
-
耳たぶを親指と人差し指ではさみ、軽く押しまわしながら刺激を与える
-
耳を耳の付け根から前(鼻の方向)に向かって倒すようにする
-
右耳の横を右手でつまんで右ひじ方向に引っ張る
2-3 耳を守るための音量チェックリスト
スマートフォンの普及により、家の中だけでなく外でもヘッドフォンやイヤホンを使って音楽を聴いたり、動画を視聴したりすることが多くなっています。
長時間大音量で音を聴き続けることは、耳に大きな負担をかけ、難聴の原因にもなります。
適切な音量を保って耳を守りましょう。

音量を抑える
多くの音楽プレーヤーやスマートフォンには音量制限機能が搭載されています。これを活用して、最大音量の60%以下を目安に音楽を聴くようにしましょう。
イヤホン・耳せんの種類を選ぶ
ノイズキャンセリング機能のあるイヤホンを使用すると、大音量にしなくても快適に聴けます。また、コンサートやライブでも専用の耳せんを使うことで、大音量から耳を守ることができます。
耳を休ませる
長時間続けて音楽を聴くことは避け、定期的に耳を休ませましょう。1時間ごとに10分程度の休憩を取ることをお勧めします。
関連ページ:音楽が難聴の原因に?耳を守る3つのルールと難聴でも音楽を楽しむ方法
2-4 定期的な耳鼻科検診のすすめ
耳の健康を守るためには、定期的に耳鼻科での検診を受けることが非常に重要です。
定期的な耳鼻科検診を受けることで、早期に異常を発見し、適切な治療を受けることができます。
特に、難聴や耳鳴りが気になる場合、早期に専門医に相談することが大切です。耳鼻科では、聴力検査や耳の内部のチェックを行い、異常があればすぐに対応できます。
また、耳の異常がなくても定期的な検診を習慣にすることで、耳の健康を守り、快適な聴覚環境を維持することができます。

関連ページ:
難聴は予防可能!加齢性難聴を予防する6つの方法と定期検診の重要性
聴力低下の原因は?隠された病気の可能性と聴力回復の可能性を解説
3 耳の日イベント
3-1 日本各地で耳の日イベントを開催
2月~3月にかけて、日本全国で耳にちなんだイベントが開催されています。ぜひこの機会に参加してみてはいかがでしょうか。
補聴器フォーラム福岡2025
日時:2025年3月2日(日)13:30~16:10
会場:アクロス福岡7F大会議場(福岡市中央区天神1丁目1-1)
第54回「耳の日」記念のつどい
日時:2025年3月2日(日)13:00~16:00(12:30開場)
会場:埼玉県県民健康センター 2階 大ホール(埼玉県さいたま市浦和区仲町3-5-1)
耳の日フェスタ
日時:2025年3月8日(土)13:00開演(12:30開場)
会場:パルテノン多摩 小ホール(東京都多摩市落合2丁目35)
「耳の日イベント」~きこえの市民公開講座~
日時:2025年3月29日(土)14:30~16:30
会場:金沢勤労者プラザ(石川県金沢市北安江3丁目2−20)
3-2 2025年東京で「デフリンピック」開催!
デフリンピックとは、デフ+オリンピックのことで、デフ(Deaf)とは、英語で「耳がきこえない」という意味です。
デフリンピックは、4年に1度開催されるデフアスリートを対象とした国際総合スポーツ競技大会で、なんと2025年の開催都市は東京!これは日本初の開催となります。
世界70以上の国と地域から選手が参加し、競技は陸上やバスケットボール、サッカーなど21競技。
デフアスリートは耳の聞こえない状態で競技を行うため、健聴者とは一味違うデフスポーツの魅力が満載。
ぜひこの機会にデフスポーツの世界を体験してみてください!
-
大会期間:2025年11月15日から26日までの12日間
-
主な会場:駒沢オリンピック公園総合運動場など

まとめ
- 耳の日(3月3日)は昭和31年、日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会が制定。日本だけでなく、耳の健康を考える日として、世界中で認識されている。
- 最新の補聴器にはノイズキャンセリングやAIを搭載し、スマホ連携など最先端の機能が搭載されている。
- 新しい生体認証技術として、耳の形で個人識別する「耳介認証」や、耳の構造を音で識別する「耳音響認証」がある。
- iPS細胞を用いた聴覚の再生医療研究が進行中
- 耳を大切にするためのセルフケア方法
- 過剰な耳掃除を避け、月1~2回程度に
- 綿棒使用、耳鼻科での耳垢除去が推奨
- 耳のマッサージで筋肉の緊張をほぐし、血流改善
- 耳の健康を守るために、音楽や動画鑑賞の際は音量は60%以下にしたり、イヤホン選び、定期的に耳を休める。
- 定期的な耳鼻科検診が大切
もし、自分の聞こえ方の状態が知りたいのなら、まずはオンラインでカンタンにチェックしてみることもできます。